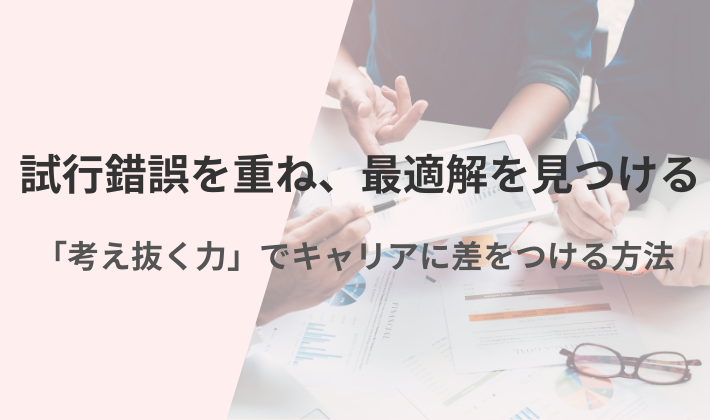仕事において「考える」とは、単なる情報処理や仕事の遂行ではなく、特に正解がない問いに対して自分なりの答えを出すことです。これを突き詰めたものが【社会人基礎力】の一つである「考え抜く力」です。
「考え抜く力」とは、目の前の課題に対して粘り強く取り組み、試行錯誤を繰り返しながら最適解を見つけ出す力のことを指します。これは、これからの時代を生き抜く上で益々重要なスキルとなります。
今回は、新しいプロジェクトを通じて「考え抜く力」を発揮するAさんの事例をもとに、このテーマを掘り下げていきます。※実在する人物ではありません
新プロジェクトの立ち上げと「考え抜く力」
Aさんは新しい商品の開発に関わるプロジェクトに携わることになりました。この商品は、業界のトレンドに基づいてアイデアでしたが、お客様に受け入れられるかどうかは不透明でした。
チーム内では「この商品は本当に必要とされるのか?」という疑問が大きな壁となり、議論は行き詰りました。多くのメンバーが「市場調査を行った通りに進めればいい」と考えていましたが、Aさんは違和感を覚えました。
「データを分析するだけでなく、自分の経験や直感も大切にする必要がある」と感じ、過去の経験を振り返り、ユーザーの声にも目を向けることにしました。「こういう機能があれば便利なのに」という意見をヒントに、新しい戦略を立て直しました。その結果、消費者の本当のニーズに応える商品へと進化し、Aさんたちの考えが新たな道を切り開くきっかけになったのです。
「考える抜く力」が求められる理由
Aさんはこの経験から、正解がない問に対して自分なりの答えを出すことの重要性を実感しました。
・自己認識の向上: 自分の価値観や経験が、判断にどのように影響を与えるかを意識することができた
・柔軟な思考の育成: データだけに頼らず、感覚や直感も大切にすることで、より創造的な解決策が生みだせ
・コミュニケーションスキルの向上: 多様な意見を交わすことで、チーム全体の質が向上する
・リスクを取る勇気: 自分の考えを持ち、発信することが自己成長に繋がる
こうした「考え抜く力」は、社会人としての基礎力の一つです。
ルーチンワークでも、新しい仕事に携わる際にも、「なぜこの作業を行うのか?」「もっと良い方法はないか?」「もっと効率的なやり方はないか?」と問い続けることで、日々の仕事に変化を生み出すことができます。
次回、第二部ではこの「考え抜く力」をどのように鍛えていくか、具体的な方法を紹介していきます。