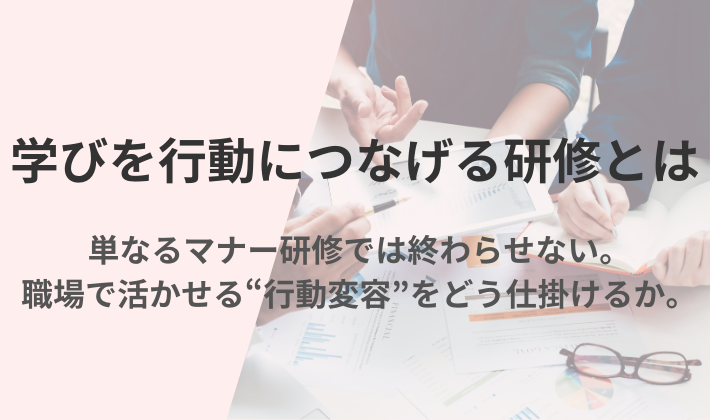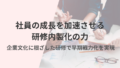新入社員研修の内製化に取り組んだ経験は、私にとって人材育成における本質を見直す大きな転機となりました。
人事部門に異動し、現場との対話を重ねる中で見えてきたのは、「外部研修だけでは補いきれない学び」が確かに存在するという事実です。
現在はキャリアコンサルタントとして、個人のキャリア支援や企業向けの研修設計に携わっていますが、当時の経験は今もなお、実務における指針となっています。
外部委託された研修は一定のクオリティが担保される一方で、自社特有の文化や現場の実情が反映されにくいという課題がありました。特に、新入社員が配属後に感じる現場とのギャップや、先輩社員とのコミュニケーションにおける戸惑いは、研修段階で解消しておくべき重要なテーマだと感じていました。
試行錯誤の末にたどり着いたのは、“企業のリアル”に寄り添った研修設計と運営です。
本記事では、研修の企画から運営、改善に至るまでのプロセスと、そこから得られた気づきやノウハウを体系的に整理し、これから内製化に取り組もうとする方々へのヒントとしてお伝えします。
自社にとって本当に必要な学びとは何か
研修の内製化にあたって最初に着手したのは、「自社にとって必要不可欠な学びとは何か」を明確にすることでした。経営層や各部門のマネージャーに対するヒアリングを通じて、以下のような視点を抽出しました。
- 自社で成果を出す人材の特徴
- 新入社員に理解・体現してほしい価値観や行動特性
- 部署間・上下関係におけるコミュニケーションの基本姿勢
この過程を通じて、「企業文化への適応」や「対人関係における基本的な姿勢の理解」といった、教科書的な内容ではカバーしきれないテーマこそが、自社にとっての最重要課題であることを再認識しました。
研修設計における行動変容の重視
研修を設計するにあたり、最も重視したのは“知識の定着”ではなく“行動の変化”です。受講後に、どのような行動が現場で見られるようになるか。それを念頭に置いて構成を考えていきました。
- 業務シーンを想定したロールプレイ
- よくある現場課題を題材にしたディスカッション
- ビジネスマナーの背景や意図を考察する演習
これにより、単なる「正解を覚える研修」ではなく、「現場で応用できる研修」へとシフトすることができました。また、座学に偏ることなく受講者の主体性を引き出す仕掛けを多数取り入れました。
研修運営における実務的な工夫と課題
内製化に伴い、研修テキストや資料の作成、進行管理、関係部門との調整など、業務負荷は非常に高くなりました。特に以下のような点に注意を払いました。
- 著作権を含む情報の取り扱い
- 実務に即した内容へのアップデート
- 受講者に配慮したわかりやすさ
また、マネージャーや先輩社員にも一部講義やワークに登壇してもらうことで、彼ら自身の“教える力”の向上にもつなげました。これは単なる運営上の工夫に留まらず、職場における育成文化の醸成にもつながったと感じています。
振り返りと改善サイクルの徹底
研修後には必ず日報を提出してもらい、受講者がどのように内容を理解・咀嚼しているかを把握しました。特に力を入れたのは、個別フィードバックの実施です。受講者が多いときは非常に大変で深夜にまで及ぶことがありましたが、それにより学びの質が確実に向上したことは、実感としてありました。
このフィードバックを次回の改善に活かすことで、毎年少しずつブラッシュアップされた研修を提供することができ、結果として“型化された研修プログラム”ではなく“進化し続ける学習機会”を作り上げることができました。
内製化による組織的効果
内製化によって、自社の文化や価値観に即した研修を実施できるようになり、配属後の新入社員の立ち上がりは格段にスムーズになりました。また、先輩社員とのコミュニケーションにおいても共通言語が生まれ、関係構築が早期に進むようになりました。
加えて、研修に関わったマネージャー層の“育成への意識”が高まり、組織全体の人材育成に対する姿勢がポジティブに変化していった点も、大きな成果の一つです。
これからの企業研修に求められること
今後、企業における研修のあり方は、さらに進化していく必要があります。新しい人材が早期に戦力化されることが求められる中で、単なる“知識提供の場”ではなく、“日常業務に直結する学び”を提供する場へと変えていくことが重要です。
加えて、デジタル教育やリスキリングといった新しい学習ニーズにも対応していく必要があります。今後も、受講者が主体的に学びたくなるような、価値ある研修設計を追求し続けたいと考えています。