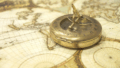「最近の若手は全然自分で考えない…」「もっと深く物事を捉えてほしいのに…」「自分で考える癖をつけて欲しい…」
そう感じているリーダーの方、いらっしゃるのではないでしょうか?
以前のブログで「新人が質問しないのはなぜ?疑問が湧かない背景と育て方」を書きましたが、今回はその続編です!
実は、この「気になったことを深掘りする力」が育ちにくいのは、部下個人の“やる気”や“能力”の問題だけではないと思っています。むしろ、彼らを取り巻く環境や、私たちが受けてきた教育、さらには日本の文化が大きく影響している可能性が高いんです。今日は、部下の「深掘り力」が育ちにくい背景と、それを引き出すためにリーダーができる3つの関わり方をご紹介します。
なぜ「深掘り」が難しいのか? リーダーが知るべき4つの背景
あなたのチームメンバーが、なぜ疑問を持たず、深く考えられないのか? その背景を理解することは、リーダーとして彼らを導く第一歩になります。
①いつも時間に追われる「多忙な日常」
「考えるより、まず処理!」
目の前のタスクに追われ、今日の仕事をこなすだけで精一杯…多くの現場がそうではないでしょうか。リーダーであるあなた自身も、そう感じているかもしれませんね。日々の業務に忙殺される中で、「なぜ?」と立ち止まって考える時間は、真っ先に削られてしまいがちです。
結果として、深く考えるよりも、効率的に答えを見つけてしまう、あるいは表層的な情報で満足してしまう習慣がついてしまうんです。
②「波風立てたくない」職場の空気
「余計なことは言わない方がいい」
疑問を口にしたり、現状に異を唱えたりすることで、「面倒な人」と思われることを恐れていませんか? もしあなたのチームや会社に、「失敗は許されない」「批判的な意見は歓迎されない」という空気が少しでもあるなら、メンバーは疑問があっても口を閉ざしてしまいます。心理的安全性が低い環境では、わざわざリスクを冒してまで「深掘り」しようとはしなくなります。
③「正解」を求められ続けた教育の弊害
「答えは一つ!」
私たちが受けてきた学校教育を思い出してみてください。多くの場合、早く正確に「正解」を見つけることが求められてきました。自ら問いを立て、試行錯誤する探求型の学びより、与えられた知識を効率よく吸収することに慣れてしまった世代が多いのです。社会に出ても、この「正解探し」のクセが抜けず、自分で深く考える機会が少なくなっているのかもしれません。
④「言わなくてもわかるでしょ」の日本文化
「空気を読んで、察してほしい」
日本の文化では、集団の調和や「和」を重んじ、あうんの呼吸で物事を進めることが美徳とされがちです。会議で異なる意見を言ったり、既存のやり方に疑問を投げかけたりすることが、場の雰囲気を壊すと受け取られることも少なくありません。
この「言わなくてもわかるだろう」という前提が、かえって思考の停止を招き、「わざわざ疑問を言語化して深掘りする」という習慣を失わせている可能性があります。
「深掘り力」を引き出す3つの関わり方
これらの要因は複雑に絡み合っていますが、リーダーであるあなたが「自分軸」を持って、チームの環境やコミュニケーションを変えていくことで、メンバーの「深掘り力」は確実に育っていきます。
「なぜ?」を歓迎する心理的安全性の高い場を作る
メンバーが「疑問を口にしても大丈夫だ」と感じられる環境がなければ、深掘りは始まりません。
- 「質問ありがとう」の徹底: どんな些細な疑問でも、投げかけられたら「良い質問だね」「気づいてくれてありがとう」と肯定的に返しましょう。質問を奨励する姿勢を明確にすることで、「質問していいんだ」という安心感が広がります。
- 「正解」より「プロセス」を評価: 「どうしてそう思ったの?」「他にどんな可能性がありそう?」といった問いかけで、思考のプロセスを促します。結果の良し悪しだけでなく、深く考えようとした姿勢や、多様な視点を持てたことを認め、褒めましょう。
- リーダー自身の「失敗談」を共有: 「実は私も昔、これで失敗した経験があるんだ」など、リーダー自身の試行錯誤や失敗談を語ることで、メンバーは「自分も完璧でなくていいんだ」と感じ、安心して挑戦できるようになります。
「対話」を通じて、思考の筋トレを促す
一方的に指示を出すのではなく、対話を通じてメンバー自身に考えさせる機会を増やしましょう。
- オープンな質問を投げかける: 「これ、どうすればいいと思う?」「この課題の根本原因は何だと思う?」など、Yes/Noで答えられないオープンな質問を意識的に投げかけます。すぐに答えを教えるのではなく、まずはメンバーに考えさせることが重要です。
- 「あなたはどう思う?」: リーダー自身の考えを提示する際も、「これはあくまで私の一意見だけど」と前置きし、メンバーの意見を引き出す余地を残します。多様な視点があることを示し、メンバーが自分の意見を持ちやすくなります。
- 「視点」を与えるヒント出し: 詰まってしまっているメンバーに対しては、「別の角度から見てみようか」「このデータから何か見えてこない?」など、直接的な答えではなく、思考のヒントや視点を提供します。これにより、メンバーは自分で答えにたどり着く喜びを感じられます。
「余白」を作り、思考の時間を与える
忙しい日々の中で「深掘り」するためには、物理的・時間的な「余白」が必要です。
- 考える時間を意図的に確保する: 会議の場で即答を求めず、「一度持ち帰って考えてみて」「次の打ち合わせまでに、いくつか案を出してみてほしい」など、考えるための猶予を与えましょう。
- 「あえて放置」する勇気を持つ: メンバーが少し悩んでいても、すぐに手助けするのではなく、まずは自分で試行錯誤する時間を与えてみましょう。もちろん、困りすぎて諦めてしまわないよう、適度な声かけやサポートは必要です。
- 非効率を受け入れる寛容さ: 「深掘り」は、時に非効率に見えるプロセスを伴います。すぐに正解が出なくても、その思考プロセス自体がメンバーの成長に繋がることを理解し、ある程度の時間や回り道を許容する姿勢を持ちましょう
最後に
深掘り力は、VUCA時代を生き抜くリーダーにとって、そしてチームを強くしていく上で、非常に重要な力です。あなたのチームでは、どんなときに「深掘り」が止まってしまっていると感じますか?
まずは今日、1on1や朝のミーティングなどで「それ、なぜそう思ったの?」とひとつ問いかけてみてください。あなたのチームが「しなやかに自分らしく働く」ために、今日からできることを始めてみませんか?