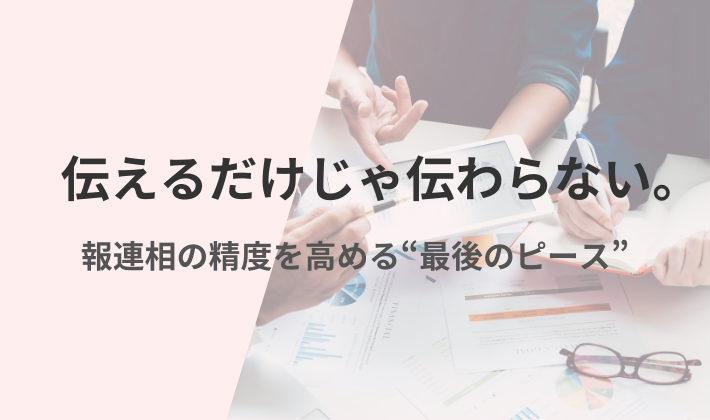「報連相」は、ご承知の通り、報告・連絡・相談のことで、新入社員研修でもだいたい前半のプログラムで教える内容です。これがしっかりと機能している組織は、業務がスムーズに進み、成果も出ていることが多いですが、報連相という言葉と重要性を知っているだけで、機能しておらず、効果を発揮できていないケースがよくあります。
「ちゃんと報連相しているはずなのに、なんでうまくいかないんだろう?」
そう感じたことはありませんか?
指示を出したのに意図とズレた行動をされる。
報告を待っていたのに、何の音沙汰もない。
実はその背景には、“伝えたつもり”と“分かったつもり”のすれ違いが潜んでいるのです。
「確認」こそが、報連相の盲点
ある上司の話。
「“これやっておいて”ってお願いしたのに、なぜか違うことをしていたんです。」
そのとき、私はこう聞きました。
「お願いしたあと、どんなふうに伝わったか、確認しましたか?」
…少し間があいて、「してませんでした」と返ってきました。
私たちはつい、“言えば伝わる”と思いがちです。でも、相手の理解は、話し手の意図とはズレていることも多いもの。
実は、ここに大きな落とし穴があります。
「わかりました」が、必ずしも“正しく理解した”という証明にはならないのです。からこそ、認識を合わせる「確認」が、報連相の中に意図的に組み込まれるべきなのです。「どう理解した?」「ここまでで合ってる?」そんな確認が、すれ違いを防ぐ力になります。
上司から部下への「報告」
部下に報告・連絡・相談を求める一方で、上司側の“報告不足”が、部下の心を遠ざけているケースもあります。
たとえば部下から「この件どうしましょうか?」と相談を受け、「一旦持ち帰って検討するね」と返したまま、報告を忘れてしまったとしたら?
部下は「忘れられたのかな…」「もう相談しない方がいいのかも」と感じ、次第に声を上げなくなっていきます。これは、相談のハードルを上げてしまい、組織全体のパフォーマンスにも影響を与えかねません。
上司も「検討中です」「○日までに返事します」と進捗を“報告”する姿勢が、部下の安心感と信頼感を生み出します。
報連相は、部下から上司へだけのものではありません。双方向に伝え合ってこそ、本当の意味で“機能する”ようになるのです。
組織に必要なのは「確認し合う文化」
報連相はただのルールではなく、信頼関係をつくる土台のコミュニケーションです。大切なのは、「伝えた」ではなく「伝わったかどうか」。そして、「聞いた」ではなく「どう理解したか」。
✅指示したら「どう理解した?」と確認する
✅相談を受けたら「検討中」「こう決めた」と報告する
✅言われっぱなし・聞きっぱなしをなくす
一方通行ではなく、双方向の確認こそが、報連相の本質です。
まとめ:確認は、相手を大切に思う行動
「ちゃんと伝わったかな」「どう理解したんだろう」そんなふうに気にかけることは、相手を大切にしている証拠です。
報連相を「伝えるための仕組み」から、「信頼を育てる対話」に進化させていきませんか?