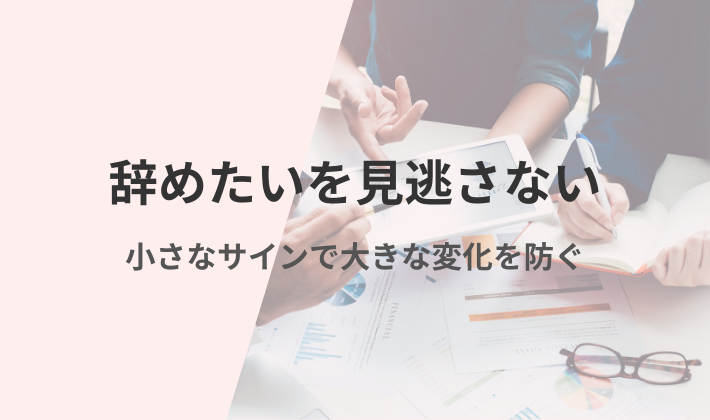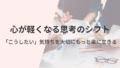部下やチームメンバーが「辞めます」と口にする時、それはすでに決断が固まっている場合が多いもの。しかし、そのような事態を未然に防ぐ方法があることをご存じでしょうか?
私が人事として勤務していたとき、退職を希望する社員との面談も担当していました。そこで強く感じたのは、社員が辞意を固めてしまった後に、そのサインを察知するのは非常に難しいということ。しかし、実際にはその決断に至る前に、必ず「小さなサイン」が隠れているのです。
今日は、これらの「小さなサイン」を見逃さず、社員が辞める前にどのように対応すべきかをお伝えします。早期に気づき、適切に対処すれば、社員の心の変化に寄り添い、退職を防ぐことができる可能性が高いのです。
小さなサインを見逃さない
ある日、課長は、部下のAさんから「辞めたい」という相談を受けました。正直、驚いたそうです。仕事に対して特に不満を口にしていたわけでもなく、表面的には順調に見えていたからです。
しかし、今になって振り返れば、Aさんが出していた「小さなサイン」を課長は見逃していました。Aさんは最近、ミーティング中に意見を出さなかったり、提出物の期限ギリギリまで遅れがちになっていたりと、些細な変化がありました。
忙しい日々の中で、その変化を「ただの疲れ」や「一時的なもの」だと軽く見てしまっていたのです。今思えば、それが「辞めたい」という大きな決断の予兆だったのかもしれません。
後から聞くと、Aさんは自分のアイデアが全く反映されず、仕事に対するモチベーションが急激に低下していたとのこと。その時点ではもう辞意が固まっており、他の選択肢を考える余裕はなかったといいます。
人は一日で辞意を決断するわけではありません。
だいたいの場合、不満や不安が積もり重なり、もう何をしても無駄だと感じる段階に至ってから「辞めよう」と決断します。「相談があります」と言葉では表現しますが、もはや「相談」ではなく「辞めますの報告」なのです。
辞めたいときのサインとは?
次のような小さなサインを見逃さないことが大切です。
口数が減ったり、意見を言わなくなる
これまで私たちの会議で意見を出していた人が、気付けば完全に黙るようになっている。
これは「もう意見を言っても何も変わらない」という不満に変わっている可能性があります。
仕事のスピードが落ちる、延びがちになる
仕事の終わりを定時ちょうどにするようになったり、ミスが増える。
これは「もう頑張る気力がない」「いつ辞めてもいいや」という気持ちの表れだといえます。
相談する機会が減る
これまで何かと相談してきた部下が、急に相談しなくなると気持ちが下がっていると考えられます。重要なことは、これらのサインに気付いたら一刻も早く声を掛けて話をすることです。あまり仰々しく声を掛けると、余計な警戒心を持ってしまうこともあるので、あくまで「自然に」です。
自分の立場的に大事になってしまいそうであれば、例えば、身近に少し上の先輩など、話を聴きやすいメンバーが居れば、その方に入ってもらうのも有りだと思います。
面談をしても「もう遅い」理由
面談でいくら話し合いをしても、部下が心の中で結論を出していることが多いのはなぜでしょうか?
それは、彼らが抱えている不満や不安が積もり積もって、「もうこれ以上無理だ」という段階に達しているからです。この段階になると、どんなに説得しようとしても気持ちが戻ることは稀です。心の準備が整いすぎていて、彼らにとって「辞める」という選択はすでに最も理にかなっている解決策なのです。
早期に手を打つためのポイント
大切なことは、部下の些細な変化や沈黙にも敏感であることです。以下のようなポイントに気をつけることで、早めに手を打つことができます。
✔ミーティングやコミュニケーションでの変化を見逃さない
普段活発に話していた人が急に無口になったり、意見を述べるのを避けるようになった場合は要注意です。これが「最初の信号」である可能性が高いです。
✔仕事のパフォーマンスに現れる変化
ミスが増えたり、納期に遅れる頻度が高くなった場合は、背後に仕事以外の問題が潜んでいることが多いです。ここで早めに声をかけ、状況を確認することが重要です。
✔感謝や褒める文化の欠如
感謝の気持ちや成果を認める文化がない職場では、部下が「自分は評価されていない」と感じやすくなります。これも退職を考える大きな原因のひとつです。
まとめ
「辞めます」と言われてしまった時点では、すでに手遅れであることが多いですが、その前にキャッチできる「小さな信号」は確実に存在します。日常のコミュニケーションを大切にし、部下が発しているサインにいち早く気づくことが、未然に対処するための第一歩です。
もちろん、すべての退職を防ぐべきというわけではありません。本人のキャリアのために必要な転職もありますし、会社にとって前向きな変化につながることもあります。
しかし、「本当は辞めたくなかった」「環境が少し変われば続けられた」 というケースは意外と多いもの。
日頃からサインをキャッチし、働きやすい環境を整えることで、不要な退職を防ぐことができるのです。早期対応が信頼関係を築き、最終的には「社員を辞めたいと思わせない環境作り」にも繋がるのです。