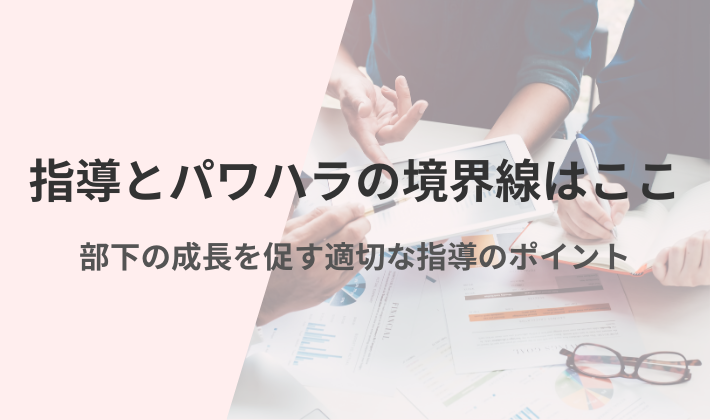まもなく4月ですね。
新入社員や、人事異動で新しいメンバーを受け入れる新たな出逢いの季節です。
どんなチームを作っていくのか考えているリーダーは多いと思いますが、近頃「すぐパワハラと言われるのが怖くて指導ができない」という管理職のお悩みをよく聞きます。
皆さんはいかがでしょうか?
部下の成長を促すはずの指導が「厳しく言うとハラスメントになるかも…」という不安から控えめになり、結果的に組織の生産性が下がってしまう。そもそも「適切な指導」と「パワハラ」の境界線はどこにあるのでしょうか?
今日は、管理職が指導を躊躇してしまう具体的なケースと、その対策を考えてみます。
管理職が指導を躊躇するケース
最近の職場では、以下のような状況で「指導を控えてしまう」ケースが増えています。
叱ることができない
ケース:「仕事のミスが続いている部下に注意したいが、強く言うとパワハラだと思われるのでは…と悩み、やんわり伝えるだけになってしまう。」
結果▶部下は気付く機会なくミスを改善できず、周りの負担が増える。
責任を追及できない
ケース:「プロジェクトの進行が遅れているが、進捗を厳しく確認すると『詰められた』と受け取られるかも…と思い深く追及できない。結果、全部自分が尻拭い。」
結果▶プロジェクトが遅延し、最終的に上司や他部署から指摘を受ける。チーム全体の統制がとれているのか
不安視される。
フィードバックを避ける
ケース:「部下のプレゼンがいまいちだったが、『ダメ出しばかりする上司』と思われたくなくて、ポジティブなことだけを伝えてしまう。」
結果▶部下の成長が遅れ、組織全体のレベルが上がらない。
目標を課せない
ケース:「営業成績が伸び悩んでいるが、目標を厳しくすると『プレッシャーが強すぎる』とハラスメント扱いされるかも…と思い、目標を下げてしまう。」
結果▶チーム全体の成績が低迷し、最終的に経営層から指導が入る。
部下の態度を指摘できない
ケース:「新人が上司や先輩に対して礼儀を欠いているが、『価値観の違い』と言われるのが怖くて指摘できない。」
結果▶組織の秩序が乱れ、チーム内のモチベーションが低下。
これって本当にパワハラ?指導との違い
「厳しく言う=パワハラ」ではありません。指導とパワハラの違いを明確にしておきましょう。
目的の違い
適切な指導:部下の成長や業務の改善
パワハラ:相手を貶める、威圧する、感情のはけ口
伝え方の違い
適切な指導:具体的な改善策を冷静に伝える
パワハラ:大声で叱責する、人格否定をする
受け手の受け止め方
適切な指導:成長につながるフィードバックとして受け取られる
パワハラ:恐怖や精神的苦痛を感じさせる
管理職が安心して指導するためのポイント
大前提ですが、厚労省が定義しているハラスメントや、職場におけるハラスメントの防止のために 等の情報を収集したり、お勤めの会社の就業規則にしっかりと目を通し、ご自身の中で「いま自分のこの指導がパワハラに抵触していないか?」の点検が必要です。定義などが曖昧だと、自信を持って指導することを躊躇してしまうことに繋がりますので、しっかりとまずは「知る」ことを行いましょう。
また、指導を躊躇してしまう背景には、「伝え方がわからない」という問題があります。適切な指導をするためのポイントを押さえておきましょう。
✔ 「叱る」ではなく「伝える」に意識をシフト
→ 「なぜこの改善が必要なのか」を論理的に伝えることで、相手に納得感を持たせる。
✔ フィードバックは「良い点+改善点」のセットで
→ いきなりダメ出しをするのではなく「ここは良かった、次はこうするともっと良くなる」と伝える。
✔ 感情ではなく、事実ベースで話す
→ 「なんでできないの!」ではなく「〇〇が足りていないから△△を意識しよう」と具体的に。
✔ 部下の成長を意識して、一貫した指導をする
→ 「指導する日」と「しない日」がバラバラだと、部下は困惑する。継続的なフィードバックが大事。
まとめ
「パワハラを恐れて指導できない」という状態は、部下の成長を妨げ、組織全体の生産性にも影響を及ぼします。指導とパワハラの違いを理解し、適切な伝え方を身につければ、自信を持って部下を育成できるようになります。指導は「叱ること」でも「怒鳴ること」でもなく、成長のチャンスを与えること、客観的事実に基づき、しっかりと相手に伝わるよう言語化して伝えることです。
適切な指導ができれば、部下の意欲を引き出し、結果として組織の力を高めることに繋がるのです。
あなたの職場では、どんな指導の工夫をしていますか?