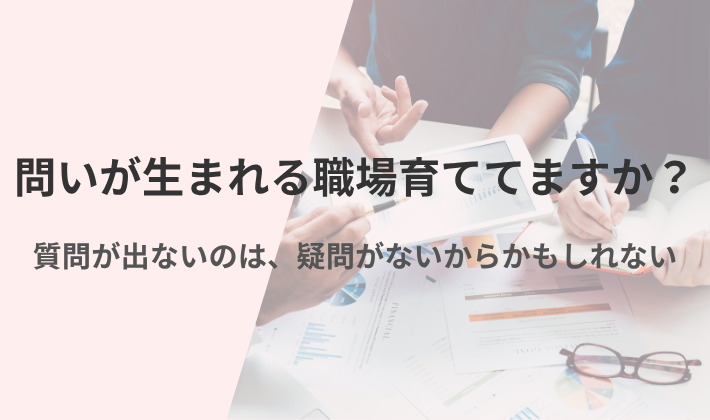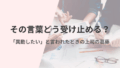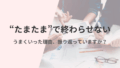「最近、若手社員から、あまり質問が出ないんですよね。興味ないんですかね。」近頃、管理職の方とお話しているとこんな声を耳にするようになりました。
「何かわからないことある?」と聞いても、「特にありません」と返ってくる。でもその後の様子を見ていると、業務がうまく進んでいない場面もちらほら見える。そんなとき、上司や先輩としては「本当にわかっているのかな?」と不安になるものです。
実際には—
「言われたことはなんとなく理解できました。でも、自分でも何がわからないのかがはっきりしないんです。とりあえずやってみます」そんな“心の声”が隠れていることも多いのではないでしょうか。
昔はもっと積極的だった…?
10年ほど前の新入社員研修を思い返すと、私が話の途中でも手が挙がり、活発に質問が飛び交っていた印象があります。ときには質問が多すぎて、研修の進行が止まるほどの熱量を感じる場面もありました。
ところが、ここ数年で少しずつその光景は変わってきました。全体の場では手が挙がらず、沈黙が続く時間も増えています。
もちろん、今も個別には質問に来る人もいます。「なぜ大勢の前だと聞けないのか?」という話は、少し奥が深いので、別の機会にするとして…
今日は一歩踏み込んで、「なぜ質問しないのか?ではなく、そもそも疑問が湧いていないのかもしれない」という視点から考えてみたいと思います。
疑問が湧かないから、質問が出てこない
質問というのは、何かに対して「知りたい」「気になる」「なんで?」「どうして?」と思うことから始まります。つまり、疑問を持つこと自体がスタートラインです。でも、最近はその“疑問”が湧きにくくなっているように感じます。
たとえばこんな会話。
「週末、買い物に行ったんだ」
「へぇ〜(それで会話終了)」
そのあとに「どこで?」「何を買ったんですか?」「何か目的があったんですか?」など、自然に広がっていくやり取りが、なかなか続きません。
これは日常会話の一場面ですが、仕事の場面でも「気になったことを深掘りする力」が育ちにくくなっている兆しかもしれません。
疑問が湧かないのは、その人の“やる気”や“能力”の問題ではなく、環境・教育・文化的背景・関心の未成熟など、さまざまな要因が影響している可能性があります。ここについても長くなりそうなので、今回はスルーすることにしましょう笑
「質問力」よりも「関心を持つ力」が弱くなっている?
質問が出ない背景には、いくつかの可能性があります。
- 人に興味を持つ経験が少ない
- 背景や理由を想像する機会がなかった
- 「これってどういうこと?」と自分の中で立ち止まる習慣がない
こうした状態では、「何か質問ある?」と聞かれても、そもそも“問い”そのものが思い浮かばないのです。
つまり、“質問する力”が足りないというよりも、「関心を持つ力」「掘り下げる力」がまだ育っていないという見方のほうが、現実に近いのかもしれません。
質問は“センス”ではなく、“習慣”で育てるもの
私が担当したある研修で、こんなワークを行いました。
「一つの言葉に対して、できるだけ多くの質問を考えてみよう」
たとえば、「朝、コンビニに寄った」という一言から、どれだけ質問を思いつけるか?というものです。よかったら読んでいる皆さんも一緒に考えてみてください。
- 何を買ったの?
- なぜそのコンビニを選んだの?
- 毎日寄るの?たまたま?
- 新商品に惹かれた?
- 時間に余裕があったの?
…と、視点を変えてみると、いくらでも質問が湧いてきます。最初は、時間を掛けて思いついた質問を、次は時間を区切って、短い時間で質問を数多く思いつくようにトレーニングするのも効果的です。
これは誰かとの会話の中でもしっかりと応用できるトレーニングです。このように、質問はセンスではなく、トレーニングや習慣で育てていくことができる力だと私は思うのです。
「わからなければ聞いて」では不十分
よくある声かけ、「わからないことがあったら聞いてね」。でもこれは、疑問が湧く土台がある人にしか届きません。大切なのは、「問いを持つための環境」を整えてあげることです。
- 小さなことに関心を持ってもいいんだ、という空気感
- 疑問を言葉にする練習の機会
- 聞いてもいいんだ、という安心感(心理的安全性)
この3つがあるだけで、「質問してみよう」と思える土壌も整います。
最後に:問いを持てる人になるために
「なんでだろう?」「もっと知りたい」「こうだったらいいのに」そんな小さな疑問や好奇心が、学びの扉を開き、成長の原動力になります。
でもその“問い”は、突然思いつくものではありません。日々の中で少しずつ「気づく力」や「興味を持つ習慣」を育てることが必要です。
だからこそ、若い世代の人たちに対して大切なのは、「質問してください」という一言ではなく、“問いを持てる感性”を育てるための関わりや、安心して疑問を口にできる職場の雰囲気なのだと思います。
問いを持てる人は、変化にも強くなります。自分で考え、自分の力で動けるようになっていく。それは、今の時代に求められる力そのものではないでしょうか。
だからこそ、私たち育成側ができるのは「問いを育てる関わり方」「問いを歓迎する空気づくり」それを意識していくことなんですよね。
続編のブログこちらも参考になりますように👇
「部下が自分で考えないのはなぜ?深堀力を引き出す3つの工夫」