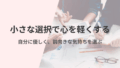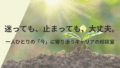ワークライフインテグレーションという言葉をご存知でしょうか?
近年、「ワークライフバランスが大事」と言われてきましたが、最近ではそれに代わる新たな考え方として「ワークライフインテグレーション」が注目されています。働き方改革の広がりによって、人々の働く意識も変化し、仕事とプライベートを両立させられる働き方へのニーズが高まり、注目されるようになりました。
私自身、企業でキャリア支援をしてきた経験に加え、現在は社外メンターとして、働く個人のキャリアに寄り添う活動もしていますが、現場で感じるのは、「仕事と私生活を切り分けること」だけが正解ではないということ。むしろ、両方をうまく“統合”することで、人生そのものが豊かになる。
そんな働き方や育成のあり方が求められていると感じています。
ワークライフインテグレーションとは?
「ワークライフバランス」と「ワークライフインテグレーション」は、どちらも仕事と生活の充実を目指す考え方ですが、アプローチに違いがあります。
ワークライフバランス
仕事と生活をきちんと分け、バランスをとる考え方。
シーソーのように、仕事とプライベートを均等に保つことを目指します。
→ 仕事の時間を減らす、休暇をしっかり取る、など時間配分に重点。
ワークライフインテグレーション
仕事と生活を組み合わせ、相乗効果を生み出す考え方。
パズルのように、仕事と生活を柔軟に組み合わせて人生全体を豊かにします。
→ 働く場所や時間にとらわれず、趣味や学びを仕事にも活かす、など統合的に。
バランスは「分ける」、インテグレーションは「つなぐ」。
どちらが良い悪いではなく、自分らしい働き方・生き方を選ぶヒントになります。
なぜ“統合”が必要なのか?
経済産業省の調査では、若手層を中心に「自分の人生全体を豊かにしたい」「仕事も家庭も諦めたくない」といった価値観の変化が示されています。また、コロナ禍を経てテレワークやハイブリッドワークが普及したことで、「働く場所」も「働く時間」も多様化しました。
こうした変化の中で、「仕事」と「私生活」を切り離すのではなく、むしろ柔軟に組み合わせて最適化することが、企業・個人の両方に求められているのです。
ワークライフインテグレーションの効果
人材育成において、ワークライフインテグレーションは次のような効果をもたらします。
経験の相互活用で、学びが深まる
プライベートで得た経験(育児、介護、地域活動、ボランティアなど)が、仕事に活かされることがあります。
逆もまた然り。仕事で培ったスキルが家庭生活に役立つことも。
これは、成人学習理論でも知られる「経験学習サイクル」にも通じます。個人の内外で得た経験をつなげることで、学びが深まり、成長が加速します。
自己決定感が育ち、エンゲージメントが向上
「自分らしい働き方」「自分で選べる柔軟性」は、自己決定理論(Deci & Ryan)でも重要視されるモチベーションの源泉。※自己決定理論(Self-determination theory(SDT))とは、1985年にアメリカの心理学者であるエドワード・デシ(Edward L. Deci)とリチャード・ライアン(Richard M. Ryan)が提唱した動機づけ(=モチベーション)理論
エンゲージメント(自発的な貢献意欲)向上に直結します。
多様なキャリアの受容と活躍を後押し
育児や介護、病気など、ライフイベントを理由に活躍の場が狭まるのではなく、その人の“今”に合わせた育成・配置が必要です。「キャリアは直線的でなくてよい」という理解が、心理的安全性にもつながります。
企業における取り組みのヒント
- リモートワークの活用:時間や場所にとらわれない評価制度の整備
- 短時間勤務・週休3日制の導入:個人のライフスタイルを尊重
- ライフイベント時の再雇用制度:キャリアの中断に寛容な仕組みづくり
- 社内メンター制度/1on1面談:定期的に「働き方」や「生活」も含めた対話の場を設ける
社外メンター制度がもたらす効果とは?
最近では、外部キャリアコンサルタントとの定期セッションを導入する企業も増加し、注目されています。また、厚生労働省が推進する「セルフ・キャリアドック制度」においても、外部キャリアコンサルタントの活用は有効な選択肢の一つとされています。
心理的安全性の向上
社内の上司や同僚には話しづらいことでも、第三者的な立場のメンターになら素直に相談できるという安心感があります。キャリアの悩み、ライフイベントの不安、価値観の揺れなども、率直に打ち明けられる環境は、メンタルヘルスの維持にもつながります。
視野が広がる
社内だけでは得られない考え方やキャリアの選択肢に触れることで、自分自身のキャリアを自分で選択していく力が育ちます。「こうでなければならない」という思い込みから自由になり、自律的なキャリア形成を後押しできます。
多様なキャリアを肯定できる
結婚・育児・介護・転勤など、人によってキャリアの形はさまざま。社外メンターとの対話によって、「自分のキャリアもありなんだ」と感じられることは、自己肯定感やモチベーションの向上につながります。
社内育成担当の負担分散と補完
育成や1on1面談は、どうしても直属上司の裁量に左右されがち。社外メンターが育成の“サポート役”に入ることで、マネジメント層の負担を軽減しつつ、育成の質を安定化できます。
離職リスクの予防
悩みを社内に抱え込んだまま、何も言わずに退職…という事態を防ぐためにも、“外の逃げ場”ではなく“対話の場”として機能させることが重要です。
私が社外メンターとして感じていること
実は私も、企業で働く従業員の皆さんに対して、社外のキャリア支援者として定期的に面談を行う場面があります。お話を聴いていると、「会社では話しにくいことを、ここでなら安心して話せる」と感じてくださる方が多くいます。
- 「家庭の事情でフルタイムは難しいけど、やりがいは失いたくない」
- 「この先の働き方やキャリアが漠然と不安」
- 「上司に相談しにくいことも、外部の視点で整理したい」
そんな声に、“答え”を押し付けるのではなく、言葉にならない想いを一緒にほどいていく。それが、社外メンターとしての私の役割だと感じています。
人材育成とは「仕事を教えること」だけではない
人材育成は単なるスキルアップの支援ではありません。その人が“人生全体”を豊かに生きる力を育てること。
ワークライフインテグレーションは、その支援の土台となる考え方です。「オンとオフをどう切り分けるか」ではなく、「どう統合していくか」。それがこれからのマネジメントの本質になるのではないでしょうか。
あなたも、自分のキャリアを話せる場所を探してみませんか?
▼続編で具体的な実践方法をご紹介しています。人生がより豊かになるヒントになれば嬉しいです。
「忙しいリーダー必見!4Lフレームワークで仕事も人生も豊かにする方法」